
校務分掌は、学校独特のしくみです。
学校の中には、教職員の中だけで使う特別な用語がたくさんあります。
今回は、そのような教育用語の中の「校務分掌」について書きます。
校務分掌
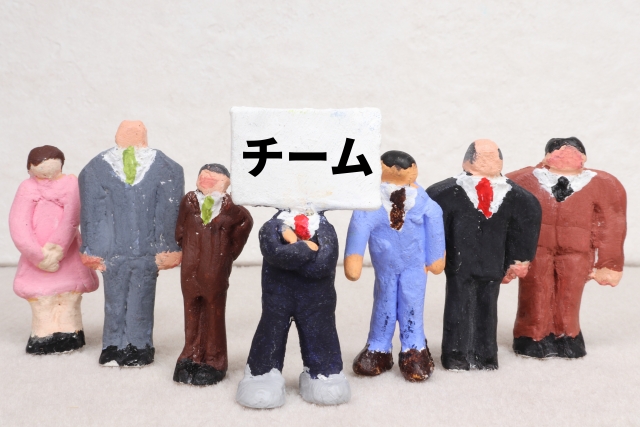
🟠校務分掌
<校務分掌とは?>
校務分掌(こうむぶんしょう)は、学校で使う特別な用語のひとつです。
校務分掌とは、教職員が学校の仕事を分担して行うことです。
学校では、潤滑に学校運営するために、子どもに授業を行う以外にも様々な仕事があります。
校務分掌には、大きく分けて、「学校運営に関する校務分掌」と、「教科の校務分掌」があります
新任の場合、簡単な仕事を受け持ち、徐々に授業以外の仕事に慣れることになります。
<校務分掌の種類>
校務分掌の名称や内容に明確な基準はありません。
校務分掌の名称や仕事範囲は学校ごとに異なります。
多くの学校では、よく似た名称のことも多いのですが、学校ごとに仕事分担には少しずつ違います。
転勤した場合、この微妙な違いに戸惑うこともあります。
ここでは、多くの学校で行われている標準的なものを挙げてみます。
・教務部
・研究部(研修部)
・生活指導部
・健康教育部
・経理部(会計部)
それぞれの部には、取りまとめる役割の部長が置かれている場合が多いです。
学校によっては、月に1回程度、○○部会という名前の「部会」を行い、学校行事などの予定を話し合ったり、職員会議で話し合う原案を作ったりすることもあります。
学校によっては、それぞれの部の中に、多くの係が作り、それぞれの係が中心になって、学校行事などの原案を提案し、部内ではあまり話し合わない方法をとっている学校もあります。
校務分掌のやり方は、学校によってかなり違いがあります。
共通していることは、学校内外の様々な仕事を教職員が分担してこなしていくということだけです。
教員の仕事がたいへんなことのひとつに、日々授業をするだけでなく、各教職員に、校務分掌が割り当てられていて、これを締切までにこなしていかないといけないことがあります。
新任教員の場合は、簡単な仕事を割り当てられることが多いのですが、経験年数が増すごとに、校務分掌の比重は重くなります。
校務分掌をどのように上手にこなしていくかどうかで、日々の労働時間が変わってくることも珍しくありません。
<教務部の仕事>
教務部の仕事は学校運営全体に関わるものが多いです。
学校のスケジュール管理や成績に関係することも行います。
多くの小学校では、管理職の次に経験のある教職員が教務主任に任命されることが多く、担任を受け持たずに、教務部の仕事を行なっていることも多いです。
授業時間も補助的に数時間受け持つことが多いです。
小学校では、体育の授業を運動場や体育館で週に3時間程度行いますが、原案がないままそれぞれの学級担任が体育の授業を決めてしまうと、同じ時間帯に、多くの学級が集まって授業ができなくなります。
そこで、教務主任が時間割の原案を作ります。こうすることで、それぞれが学級がスムーズに授業を行うことができます。
このように学級毎に割り当てを行う教科等には、理科室・図書室・音楽室・図工室・PC室・家庭科室などがあります。
学校の規模や実情に応じて、どのような時間割の原案を作成するのかは変わってきます。
最近は、国語や算数の授業には、習熟度の担当の教員が入ることがあります。このような教科についても、教務主任などが原案をきちんと作成していないと、教員がそれぞれの学級にうまく入れなくなります。
各月の学校行事の予定を作ったり、学校便りを作成したりするのも教務主任の仕事になっていることがあります。
<研究部(研修部)の仕事>
授業の質を高めるための手立てを講じるのが研究部の役割です。学校によっては、研修部という場合もあります。
研究部(研修部)にも、中心に仕事を行う研究主任がいることが多いです。
研究部では、研究主任が中心になって研究教科や研究テーマなどを設定して校内研究組織を作ります。
教員の授業力向上のために、年に数回研究授業を行うことがあります。
年間の研修のスケジュールを作ったり、研究授業の日程が重ならないように日程調整を教務主任を一緒に調整したりします。
研究授業を行うときに、外部講師との調整を行うこともあります。
研究授業の前の指導案検討会の司会をしたり、研究授業後の研究授業討論会の司会をしたりすることもあります。研究授業の授業記録をとることが、研究部の仕事になっていることもあります。
<生活指導部>
日々の学校生活における子どもの生活面の業務を担当します。
生活指導部長が任命されている学校も多いです。
学校のきまりを作成したり、生活指導上の月や週のめあてを設定したりします。
週に一回行われる全校朝会の司会や児童集会の司会を生活指導の教員が行うこともあります。
児童会や委員会、クラブ活動の計画を作成するのも生活指導部の役割のひとつです。
子どもが問題行動を起こした場合は、担任や学年主任と一緒に、生活指導部長が子どもの話を聞くこともあります。
登下校指導の計画を作成したり、いじめ対応の計画を作成したりすることもあります。
<教科・領域の分担>
教科・領域の校務分掌として、それぞれの教科・領域にひとりずつ「主任」を決めることがあります。
教科主任・領域主任は、それぞれの教科や領域の学校の代表として、他校との調整を行なったり、学校内で、その教科や領域の推進業務を行なったりします。
地域によっては、自治体にある学校で協力して、作文集を作ることがあります。そのような場合、国語主任が中心になって、他校との連絡調整作業を行ったり、学校代表の子どもの作品を選んだりします。
⭐️ ⭐️
関係する言葉についてもお読みください。
発問:教育用語①に進む(内部リンク)
板書:教育用語②に進む(内部リンク)
机間指導:教育用語③に進む(内部リンク)
教材:教育用語④に進む(内部リンク)
リライト教材:教育用語⑤に進む(内部リンク)
研究授業:教育用語⑥に進む(内部リンク)
オノマトペ:教育用語⑦に進む(内部リンク)
教育課程:教育用語⑨に進む(内部リンク)
週案:教育用語⑩に進む(内部リンク)
スタートカリキュラム:教育用語⑪に進む(内部リンク)
分かち書き:教育用語⑫に進む(内部リンク)

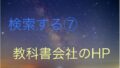
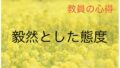
コメント