
新しい教材の「はるねこ」の教材分析について知りたいです。
よい授業をするためには、ていねいな教材研究をすることは大切です。
しかし、国語の教材の分析をするのは時間がかかります。
そこで、大まかな教材分析例を提示することにします。
今回は、2年生の教科書に載っている「はるねこ」の教材分析をします。
この教材は、2024年(平成6年)の4月から採択されている教科書で新たに付け加えられた教材です。
はるねこ:教材分析

🟠はるねこ:教材分析
この作品は、教育出版2年生の教科書に載っています。2024(令和6)年からの新教材です。
<作者>
かんのゆうこさん文
松成真理子(まつなり・まりこ)さん絵
出典:「はるねこ」(講談社・2011年)。NHK・Eテレ「おかあさんといっしょ」にて、絵本朗読劇として放映されたほか、多くのラジオ番組などでも取り上げられている絵本です。
かんのゆうこさんについて
日本の児童文学作家です。東京都で生まれです。
東京女学館短期大学・文科を卒業しました。会社勤務を経て作家デビューしました。
2024年現在、国内外合わせて50冊の絵本や児童書を出版しています。
「見えるものの奥にある、もう一つの物語」をテーマに、 物語を書き続けています。
主な著作に「ふゆねこ」(講談社・2010年)、「なつねこ」(講談社・2011年)、「あきねこ」(講談社・2011年)、「はりねずみのルーチカ」(講談社・2013年)などがあります。
<題名>
題名は「はるねこ」です。
題名から、春に関係するねこだということがわかります。
題名を読むだけでは、猫の名前なのか、どのように春に関係しているかわかりませんが、子どもにとってとても興味をひく題名です。
このお話には、ねこシリーズの「ふゆねこ」「なつねこ」「あきねこ」があります。
<設定>
いつ(時):きらきらこもれ日のゆれるはるの日。
どこ(場所):あやの家。
だれ(登場人物):あや。
<人物>
はるねこ……主人公。あやに手がみを出す。
あや……はるねこをたすけた女の子。
<あらすじ>
後程、付け加えます。
<場面>
この物語は、場面と場面の間に1行空きで、5つの場面に分けて書かれていますので、場面を5つに分け、1場面を30~40字程度にまとめてみます。
① はるの日、あやのもとに、はるねこからおれいの手がみときんちゃくぶくろがとどいた。
② きょねんの今ごろ、はるが来ないまま、あやがそとを見ると、ねこが何かをさがしていた。
③ 「はるのたねをなくした」とはるねこがいうので、おりがみではるをつくることにした。
④ おりがみの花は本物の花になり、本当の春がやってきたので、はるねこはかえった。
⑤ 一年まえのことを思い出し、手がみを読むと、「ひだまりのたね」をおくるとあった。
1234567890123456789012345678901234567890
<人物の会話>
このお話には、あやとはるねこの二人しか出てきません。
ですから、会話も二人のものしかありません。
会話文は2つの方法に分かれます。
1つは、あやが独り言を言っているものです。
最初と最後に出てきます。
・「あ、これは、もしかして、あのときの……。」
・「早くあったかいおそとであそびたいなぁ。」
・「あのときは、たのしかったなあ。」
もう1つは、あやとはるねことの会話です。
次のようなやりとりが始まりです。
・「こんにちは、ねこさん。どうしたの。」
「ああ、もうどうしたらいいんだろう。あれがないと、ことしのはるはやってこない。こまった、こまった、どうしよう。」
「ええっ。はるがやってこないの。」
「ぼくは、はるねこ。まいとし、はるをはこぶことが、ぼくのしごとなの。それなのに、ぼくったら、たくさんの『はるのたね』がつまったきんちゃくぶくろを、どこかにおとしちゃったんだ。」
「だから、ことしのはるは、なかなかやってこなかったのね。」
そして、あやはいいことを思いつきます。
・「そうだ。このおりがみで、いっしょにはるをつくってみようよ。」
「えっ。そんなことできるのかい。」
「やってみるのよ。さあ、はるねこさんもてつだって。」
本当の春がやってきた後で、はるねこはあやにお礼を言った後で、次のようにたのみます。
・「ああ、ほんとうによかった。ことしはきみのおかげで、ぶじにはるがやってきたよ。」
「ぼくはそろそろはるのくにへかえらないといけないの。」
「いつもはつよいかぜにのって、はるのくにまでかえるんだ。だから、かぜを、おりがみでつくってくれないかなあ。」
「ううん、つよいかぜねえ。ああ、それだったら……。」
<人物の行動>
二人の春をつくる行動は次のように始まります。
・あやとはるねこは、たのしくうたいながら、たくさんの花をつくりはじめました。
するとどうでしょう……。
二人は、いつのまにか、ひろいひろいのはらのまん中にすわっていました。
そこで、あやとはるねこは、おりがみでつくった色とりどりの花を、さあっと、のはらにふりまきました。
おりがみの花は、あっというまに本物の花になって、あまいかおりでいっぱいにあふれたのです。
このようにして、二人は春を作り始めました。
<主題>
この物語の主題は、何でしょうか?
「はるねことの出会いとはるをつくること」を、あやが体験したことなのかもしれません。
本当は、春の訪れなどの季節の変化は地球の公転で起こります。
でも、このお話では、はるねこが、はるのたねを運ぶことではるがおとずれることになっています。
でも、そのはるのたねをはるねこがなくしてしまい、はるがきません。
そこで、あやの思いつきで、二人ではるをつくることにします。
ファンタジー溢れる楽しいお話です。
<表現の工夫>
このお話での表現の工夫の一つは、お話の構成が「額縁構造」になっていることです。
「額縁構造」というのは、絵画と額縁の関係のように、導入部のお話を外枠として、その内側に、別のお話を埋め込んでいき、再度、元のお話に戻るというように、入れ子構造の物語の形式のことです。
特にこのお話では、3つの枠組みが存在します。
1つめは、手紙。2つめは、今年のあや。3つめは、昨年のあやとはるねこのやりとりです。
まず、1つ目のはるねこの手紙がお話の最初と最後にあります。
その手紙を読むのは、今年のあやです。これも最初と最後に書かれています。
今年のあやは、去年のはるねことの出来事を思い出す、という形式で、物語の大部分が作られています。
<まとめにかえて>
この教材分析は、このブログに載せている「物語文の教材研究の仕方」に挙げた10個の視点のうち、最後の指導計画を除いた9つの視点に基づいて行ったものです。
教員のみなさん1人1人が自分で行う教材研究の参考になれば幸いです。
⭐️ ⭐️
この記事とは関係がないのですが、少し宣伝をさせてください。
このブログを運営しています鴫田岡明(しぎた・おかあき)監修で、YouTubeの漫画動画を主に小学校の子ども向けに作って公開しています。これまでに5つ作っているのですが、最新作のテーマは、「万博」です。
いろいろと言われている万博ですが、実際に行ってみて感じたことは、やはりとても楽しいところだということです。
今回は、「万博ってなに?」という題名で作って、公開しています。
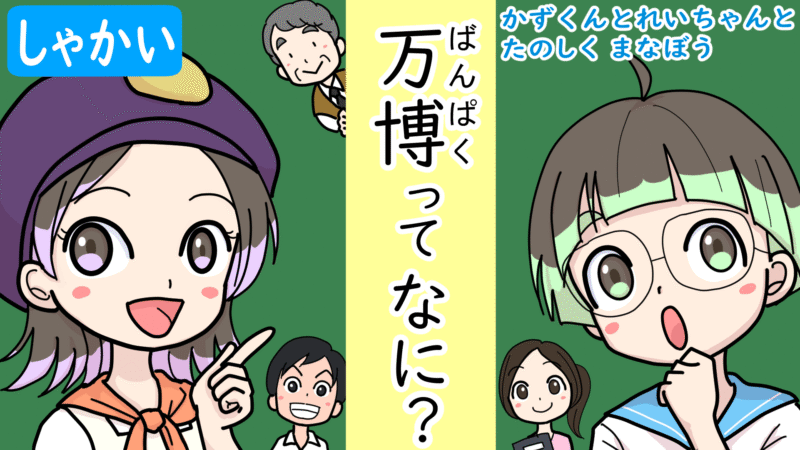
「万博ってなに?」「なにがあるの? なにがすごいの?」
「今回の関西大阪万博の展示物には、なにがあるか?」
「参加国は何か国ぐらいあるか?」「万博っていつから始まったの?」
「大阪・関西万博のテーマってどんな意味?」
などについて説明しています。
ぜひ、多くのお子さんや保護者のみなさん、先生などの教育関係者のみなさんにも見てほしいです。
次のところから見ることができます。
Youtube漫画動画「万博ってなに?」に進む(外部リンク)
物語文の教材研究については、次のページもお読みください。
物語文の教材研究の仕方(1)基本的な考えに進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(2)視点に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(3)設定・人物に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(4)あらすじ・場面に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(5)会話・行動に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(6)主題に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(7)表現の工夫に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(8)指導法に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(9)指導方法に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(10)目標と教材の関係に進む(内部リンク)
他の教材の教材分析については、次のページをお読みください。
かさこじぞう 教材分析007に進む(内部リンク)
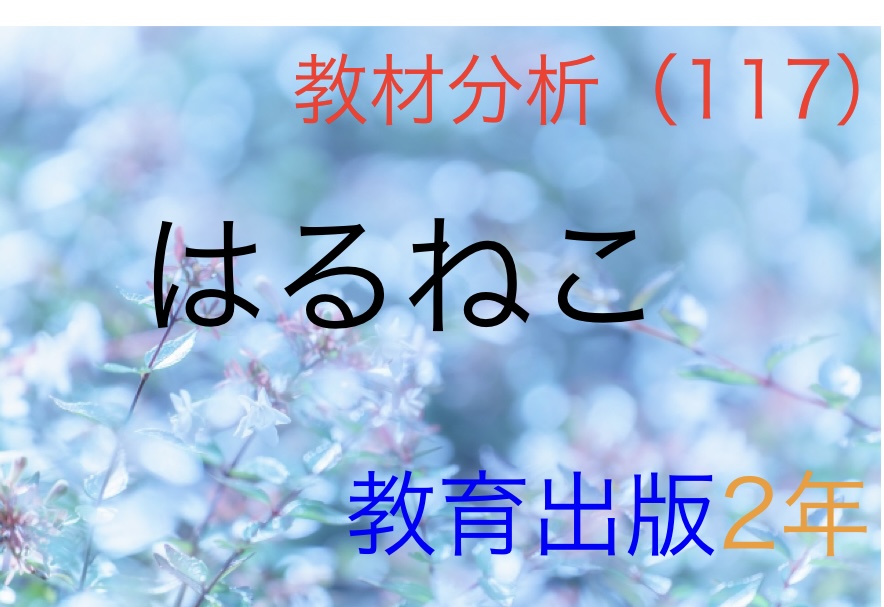

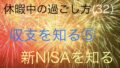
コメント