
朝の会の仕方について気になることがあります。
多くの学級で、朝の会や帰りの会の司会を子どもに任せていると思います。
今回は、「朝の会の司会」について書きます。
朝の会の司会

🟠朝の会などの変な司会
朝の会や終わりの会をしている学級は多いように思います。
その際、輪番制で、子どもに司会を任せている学級もあると思います。
子どもが司会をすることは、人前に出て、話す機会が増えて、良いことだと思います。
しかし、時々、子どもの司会の仕方や話し方で気になることがあります。
1つめは、2人組の司会にしていて、その2人の子どもが、声をそろえて司会をしていることです。
2つめは、司会の仕方の紙を見ながら、それに目を落として、読んでいることです。
この2つの結果、二人の声を揃えるために、話す言葉がゆっくりとしていて、独特の変な抑揚のある話し方になっていることがあります。
例えば、次のような話し方です。
「これからあ、朝のを、会おを、始めます。初めにい、先生とお、朝のを、挨拶おをします。」
日常生活では、あり得ないような変な話し方になっています。
🟠解決方法
では、どのようにすれば、このおかしな司会の仕方をやめさせることができるのでしょうか。
答えは、簡単です。
司会の二人に、交代で話をさせることです。
自分のペースで、話すことができますから、変な話し方をする必要がなくなります。
そして、できれば、司会の仕方の紙を見るのはいいのですが、声を出す時は、紙から目を離し、みんなの方を見て、声を出すようにするとよいと思います。
覚える必要はありません。何回見てもいいので、声を出す時だけ、紙を見ないようにするとよいのです。
この2つに注意するだけで、自然な話し方になります。
🟠朝の会で司会がするとよいこと
朝の会の時に、交代で、1分間スピーチなどをしている学級もあると思います。
その時に、司会がするとよいことの1つに、司会を前でするのではなく、学級の後ろに立ってするということがあります。
司会の子どもが、後ろに立つことで、1分間スピーチをする子どもの声が、きちんと学級の後ろまで届いているかどうかがよくわかります。
例えば、司会の子どもには、スピーチする子どもの声が聞こえていたら、大きく両手で丸をつくるように伝えたり、声が小さいときは、口の前で、手を閉じたり広げたりして、もっと声を大きくするようにジェスチャーで伝えるようしておくと、自然とスピーチをする子どもの声も大きさを調節できるようになると思います。
スピーチの後、最初に、司会の子どもがスピーチの声の大きさや話す内容について、簡単な感想を伝えたり、質問をしたりするとよいでしょう。こうすることで、司会になれば、感想や質問を言う機会が、必ず与えられることになります。
学級で、一部の積極的な子どもが発言を独占することの弊害が、このことだけでも減ることになります。
司会の子どもが感想や質問をした後で、他の子どもに感想や質問などのやりとりをするようにすると、よいと思います。
⭐️ ⭐️
なお、あわせて、次のページもお読みください。
何をめざすのか 話すこと・聞くことの指導(1)に戻る(内部リンク)
道順をどう話すか 話すこと・聞くことの指導(2)に戻る(内部リンク)
話すことに慣れる 話すこと・聞くことの指導(3)に戻る(内部リンク)
発言の機会を増やす. 話すこと・聞くことの指導(4)に戻る(内部リンク)
ショウアンドテル. 話すこと・聞くことの指導(6)に進む(内部リンク)
本の紹介. 話すこと・聞くことの指導(7)に進む(内部リンク)
話す指導で思うこと 話すこと・聞くことの指導(8)に進む(内部リンク)
聞く時の構え 話すこと・聞くこと(9)に進む(内部リンク)
インタビュー 話すこと・聞くこと(10)に進む(内部リンク)
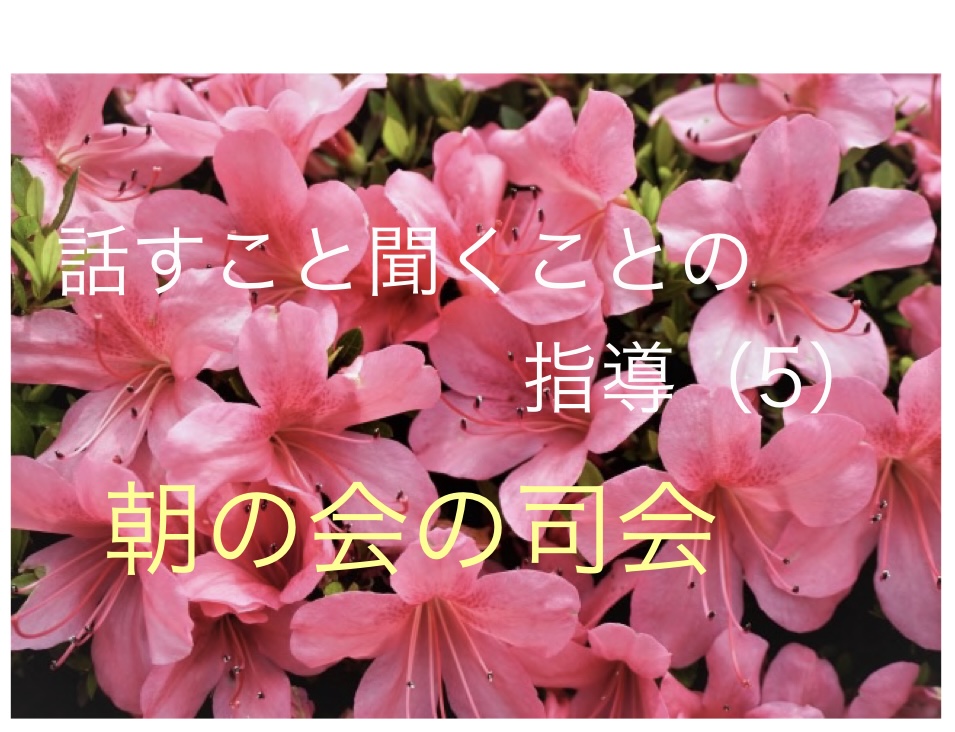
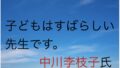
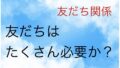
コメント