
「帰り道」の教材分析について知りたいです。
よい授業をするためには、ていねいな教材研究をすることは大切です。
しかし、国語の教材の分析をするのは時間がかかります。
そこで、大まかな教材分析例を提示することにします。
今回は、6年生の教科書に載っている「帰り道」の教材分析をします。
帰り道:教材分析

🟠帰り道:教材分析
この作品は、光村図書の6年生の教科書に載っています。
<作者>
森絵都(もり・えと)さん作
スカイエマさん絵
出典:この教科書のために書き下ろしされています。
森絵都さんについて
1968年(昭和43年)生まれです。日本の小説家、児童文学者です。
東京生まれです。日本児童教育専門学校卒業後、早稲田大学を卒業しました。
1990年に「リズム」で第31回講談社児童文学新人賞を受賞してデビューしました。同じ作品で、第2回椋鳩十児童文学賞も受賞しています。
第46回産経児童出版文化賞を受賞した「カラフル」(1999年・理論社)はアニメ映画化されました。
第52回小学館児童出版文化賞を受賞した「DIVE‼︎」(2003年・講談社)は、テレビアニメ化、アニメ映画化、実写ドラマ化、実写映画化、舞台化されています。
「風に舞いあがるビニールシート」(2006年・文藝春秋)で第135回直木賞を受賞しています。
<題名>
題名は「帰り道」です。
学校の帰り道の出来事について書かれた内容だと予想できます。子どもにとって日常的にしていることです。
<設定>
いつ(時):放課後
どこ(場所):学校の玄関口。
だれ(登場人物):周也、律。
<人物>
律……主人公のひとり。最初の話者。
周也……もうひとりの主人公。2人めの話者。
友達……昼休みに、「どちらか好きか」という話をする。
<あらすじ>
一(律の視点)
・放課後の玄関口で、周也から声をかけられどきっとした。
・周也はいつも野球の練習なのに、今日はないとのこと。いっしょに帰る気のようだ。
・小四から同じクラスの周也。家も近く、周也が野球を始めるまでいっしょに登下校していた。
・今日のぼくには、周也と二人きりの帰り道がはてしなく遠く感じられる。
・今日の昼休み、友達五人でしゃべっていた。「どっちが好き。」という話になった。
・みんなで順に質問し合い、ぽんぽん答えていくが、そのテンポにぼくだけついていけない。
・一人でごにょごにょ言ってたら、周也がぼくをにらんだんだ。
・「どっちも好きってのは、どっちも好きじゃないのと、いっしょじゃないの。」
・先のとがったものが、みぞおちの辺りにずきっとささった。今もささっている。
・返事をしないぼくに白けたのか、周也の口数も減り、二人してたまりこんだ。
・周也とぼくの間にきょりが開く。これからも周也はずっとテンポよく前へ進んでいくだろう。
・どうして、ぼく、すぐに立ち止まっちゃうんだろう。
・歩道橋の近くでは、ぼくは周也に三歩以上のおくれをとり、もう、おいつけない。
・天をあおぐと、信じがたいものを見た。空一面からシャワーの水が降ってきた。
・体中に打ちつける水滴を雨と認めるのに、少し時間がかかった。
・晴れているのに雨なんて、不自然すぎる。ぼくと周也はむやみにしたばたした。
・たがいのぬれた頭を指さし合って笑った。気がつくと、みぞおちの異物が消えてきた。
・はしゃいだばつの悪さをかくすように、すっと目をふせると、水たまりがきらきら光る。
・今だ、と思った。今、言わなきゃ。きっと二度と言えない。
・「ぼく、晴れが好きだけど、たまには、雨も好きだ。ほんとに、両方好きなんだ。」
・周也はまじまじとぼくの顔を見つめこっくりうなずいた。
・周也にしてはめずらしく言葉がない。なのに、分かってもらえた気がした。
・「行こっか。」「うん。」
・ぬれた地面はさっきよりも軽快な足音をきざみ、ぼくたちはまた歩き出した。
二(周也の視点)
・何もなかったみたいにふるまえば、何もなかったことになる。そんなあまい考えはすてた。
・校門を出てから数分後、最初の角を曲がった辺りだった。
・どんなに必死で話題をふっても、律は、うんともすんとも言わない。律はおこっているんだ。
・昼休み、みんなで話をしているとき、はっきりしない律に、言わなくてもいいことを言った。
・まずい、と思うも、もうおそい。以降、絶対にぼくの顔を見ようとしない。
・律のことが気になって、野球の練習を休んで、玄関口で待ちぶせた。
・何を言っても、背中ごしに聞こえてくるのは、さえない足音だけ。
・ふいに母親の小言が頭をかすめた。
・「あなた、おしゃべりなくせに、どうして会話のキャッチボールができないの。」
・たしかに、ぼくの言葉は軽すぎる。ぽんぽん、むだに打ちすぎる。
・もっとねらいを定めて、いい球を投げたら、律だって何か返してくれるかな。
・考えたとたん、舌が止まった。あわてるほどに口は動かなくなる。ぼくは静けさが苦手。
・正確にいうと、だれかといるときのちんもくが苦手。そわそわと落ち着きをなくす。
・そっと後ろをふり返ると、今日も律はおっとりと一歩一歩をきざんでいる。
・木もれ日をふりあおぐしぐさにも、よゆうが見てとれる。ぼくにはない落ち着きっぷり。
・とつぜん、律の両目が大きく見開かれた。なんだ、と思う間もなく、ほおに一滴が当たった。
・天気雨。玉のことばかり考えていたので、空から降ってくるそれが、白い球みたいにうつった。
・ぼくたちは全身に雨を浴びながら、しばらくの間ばたばたと暴れまくった。
・何もかもがむしょうにおかしくて、笑いがあふれた。律も笑ってくれたのがうれしかった。
・はっとしたのは、爆発的な笑いが去った後、律がひとみを険しくしてつぶやいたときだ。
・「ぼく、晴れが好きだけど、たまには、雨も好きだ。ほんとに、両方好きなんだ。」
・たしかにそうだ。どっちも好きってこともある。心で賛成した。
・ぼくはとっさにそれを言葉にできなかった。できたのはだまってうなずくだけ。
・なのに、なんだか律は雨上がりみたいな笑顔にもどって、うなずき返した。
・「行こっか。」「うん。」
・律と並んで歩きだしながら、思った。ー投げそこなった。でも、ぼくは初めて、律の言葉をちゃんと受け止められたのかもしれない。
<場面>
物語を、このブログで紹介している方法で、場面を5つに分け、1場面を30~40字程度にまとめてみます。
この物語では、1つの出来事を律と周也の視点から描かれています。それぞれを五場面で書きます。
律の視点
① 放課後の玄関口に、周也がいた。いっしょに帰る気のようだが、ぼくは気が重い。
② 昼休み、友達との、どっちが好きと話で、周也に、ひどい言葉をかけられた。
③ ずっとテンポよく進む周也に、会話も足取りもおくれをとり、おいつけない。
④ 突然の雨で笑った時「晴れも、雨も、両方好きだ。」と自分の気持ちが言えた。
⑤ 周也はうなずいてくれた。分かってもらえた気がした。二人で軽快に歩き出した。
周也の視点
① 何もないことにできないと気づいたのは、最初の角を曲がった辺りだった。
② 律に言わなくていいことを言った。野球の練習も休み、話しかけるが、返事はない。
③ 母から言われた「会話のキャッチボールができない」という言葉が重くのしかかる。
④ 突然の天気雨。笑い合った後、律は、「晴れも、雨も、両方好きだ。」と言った。
⑤ 言葉は出ないでうなずいただけ。でも、ぼくは初めて律の言葉をちゃんと受け止められた。
1234567890123456789012345678901234567890
<人物の会話>
この物語には重要な会話がいくつかあります。
二人の関係がぎくしゃくしたのは、「どっちが好きか」という話題のときに、律さんが、みんなのように、どちらかはっきりした答えを言えないで、「どっちかなあ。」とか「どっちもかな。」と一人でごにょごにょ言っていたら、周也が言った次の言葉です。
・「どっちも好きってのは、どっちも好きじゃないのと、いっしょじゃないの。」
この言葉をきっかけにして、二人の気持ちは離れます。テンポの違いに戸惑う律。
言ってはいけない言葉を言ったと反省し関係を修復しようと試みる周也。
その時、突然の天気雨が二人をおそいます。笑い合った後、律は言います。
・「ぼく、晴れが好きだけど、たまには、雨も好きだ。ほんとに、両方好きなんだ。」
どっちも好きっていう場面を、二人は一緒に体験することで共感できます。
こうして、二人の関係は、無事修復できました。めでたし、めでたし。
<人物の行動>
この物語のおもしろさは、同じ場面を二人の視点で描いていることです。お互いに相手が何を思っているのかは知りません。全てを知っているのは、この物語の作者である森絵都さんと読者である私たちだけです。
一度こわれたかけた二人の関係が、徐々に修復されていきます。
玄関口で待つ周也の行為を快く思っていないことは、律の次の行動からわかります。
・もたもたとくつをはきかえて外へ出る。
また、周也のテンポに追いつけなくて戸惑う気持ちは、律の次の行動からもわかります。
・ぼくは周也から三歩以上おくれをとっていた。もうだめだ。追いつけない。あきらめの境地でぼくは天をあおいだ。
しかし、天気雨に出合ったことで、二人の気持ちは少し和らぎます。
・ぼくと周也はむやみにじたばたし、意味もなくとんだりはねたりして、またたく間に天気雨が通り過ぎていくと、たがいの頭を指さし合って笑った。
そして、次の周也の行動を見ることで、律は安心します。
・周也はしばしまばたきをとめて、まじまじとぼくの顔を見つめ、それから、こっくりうなずいた。周也にしてはめずらしく言葉がない。なのに、分かってもらえた気がした。
<主題>
この物語の主題は、何でしょうか?
「思春期の子ども同士の気持ちのすれ違いと修復」なのかもしれません。
私たちは、自分の気持ちはなんとかわかりますが、相手の考えていることなんて、なかなか言葉を使っても理解できないことが多いです。
この物語の前半、あまり深く考えないで言った言葉に傷つく律さんに対し、なんとか関係を修復しようと言葉を尽くす周也さんの関係はなかなか改善しません。しかし、普段無口で自分の気持ちを上手く言えない律さんの言葉を周也さんが黙って頷くことで修復します。その様子を、森絵都さんが見事に描いています。さすが、直木賞受賞作家だと感心します。
<表現の工夫>
表現の工夫はたくさんあります。この物語は、すべてそれぞれの子どもの視点から描かれていますが、普通の6年生では描くことのできないような見事な表現がたくさん散りばめられています。
ここでは、情景描写を取り上げます。情景描写の中に、二人の気持ちが巧く描かれています。
・もたもたとくつをはきかえて外へ出ると、五月の空はまだ明るく、グラウンドに舞う砂ぼこりを西日がこがね色に照らしていた。
・ぬれた地面にさっきよりも軽快な足音をきざんで、ぼくたちはまた歩き出した。
<まとめにかえて>
この教材分析は、このブログに載せている「物語文の教材研究の仕方」に挙げた10個の視点のうち、最後の指導計画を除いた9つの視点に基づいて行ったものです。
教員のみなさん1人1人が自分で行う教材研究の参考になれば幸いです。
初雪のふる日 教材分析001に進む(内部リンク)
世界一美しいぼくの村 教材分析002に進む(内部リンク)
世界でいちばんやかましい音 教材分析003に進む(内部リンク)
大造じいさんとガン 教材分析009に進む(内部リンク)
海の命 教材分析020に進む(内部リンク)
雪の夜明け 教材分析023に進む(内部リンク)
物語文の教材研究については、次のページもお読みください。
物語文の教材研究の仕方(1)基本的な考えに進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(2)視点に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(3)設定・人物に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(4)あらすじ・場面に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(5)会話・行動に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(6)主題に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(7)表現の工夫に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(8)指導法に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(9)指導方法に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(10)目標と教材の関係に進む(内部リンク)

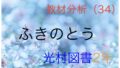
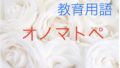
コメント