
読書感想文の書き方について知りたいです。
夏休みの宿題として、「読書感想文」が出されることがあります。
しかし、読書感想文の書き方が国語の授業で指導されることはあまりありません。
そこで、今回は、「読書感想文」について書きます。
読書感想文

🟠読書感想文
<読書感想文>
東京書籍の出版している5年生の教科書には、「文章の種類」という国語科の学習で出てくる言葉について解説しているページがあります。
そこには、「意見文」「記録文」「報告文」「感想文」「物語」「詩」「短歌」「俳句」という言葉が並び、「感想文」には、次のような説明が書かれています。
ある物事について、自分が感じたり思ったりしたことを伝える文章。生活の中で感じたり思ったりしたことや、本を読んで感じたり思ったりしたことを伝える文章などを指す。
新しい国語 五 東京書籍
一般的には、読書感想文以外の場面で「感想文」という言葉を目にすることはないのですが、東京書籍では、このように「感想文」という言葉を用いています。
そして、伝記教材である「手塚治虫」の教材を読み、「伝記を読んで感想文を書こう」という単元を設定しています。
ただ、夏休みの宿題として、多くの学校で出されるような読書感想文を書くという設定にはしていません。
東京書籍では、「手塚治虫」さんの伝記を読み、手塚治虫さんの考えや生き方を読み取る学習になっています。その後で、手塚治虫さんの生き方について感じたことを感想文という形で文章に書き、友だちと交流することにしています。
その後、自分の興味を持った人物の伝記を読み、感想文を読み、感想を伝え合うことにしています。
光村図書の5年生の教科書では、「なまえつけてよ」という物語文を教材として取り上げ、「登場人物どうしの関わりをとらえ、感想を伝え合おう」という単元を設定しています。
ここでも、感想を伝え合う活動は設定していますが、読書感想文の書き方を伝えているわけではありません。
今回は、私なりの考える読書感想文の書き方について説明します。
<なぜ読書感想文が課題として出されているのか>
ところで、なぜ、夏休みの宿題として読書感想文が出されているのでしょうか。
その理由は、極めて簡単です。全国学校図書館協議会と毎日新聞社が主催する「青少年読書感想文全国コンクール」が開催されるからです。そして、多くの学校では、このコンクールに参加するようにしていることが多いからです。
青少年読書感想文全国コンクールに進む(外部リンク)
このコンクールの趣旨は、次の通りです。
子どもや若者が本に親しむ機会をつくり、読書の楽しさ、すばらしさを体験させ、読書の習慣化を図る。
より深く読書し、読書の感動を文章に表現することをとおして、豊かな人間性や考える力を育む。更に、自分の考えを正しい日本語で表現する力を養う。
青少年読書感想文全国コンクール・応募要項・本コンクール開催趣旨
ただ、明確な書き方も教えないまま、コンクールへの参加をうながし、本を読んで感想文を書けというのは少し乱暴な話です。子どもの中には、読書感想文を書かないといけないので、読書がきらいになったと思う子どももいます。こうなってくると、素晴らしい趣旨とは真逆の実態になっているのは悲しいことです。
ただ、具体的に詳しい書き方が書かれているわけではありませんが、「感想文Q&A」で「何をどう書けばいいか、全く分かりません。」という質問に答える形で次のような説明があります。
本を読んで自分がどこに感動したのか、なぜ感動したのかを考えましょう。そしてもう一度本を読んでみましょう。自分の生き方や経験と本の世界とを照らし合わせると、いろいろなことが見えてきます。感じたこと、思ったこと、連想したことなどを忘れないうちに全部メモしておきましょう。そうしたら、順番を入れ替えたり内容を補ったりして、どう書けば自分の心の動きにぴったりするか、それがうまく人に伝わるかを考えましょう。先生や家の人と相談してみるのもいいでしょう。そうするうちに何をどう書けばいいのか、自分が一番言いたいことは何なのかがはっきりしてきます。書き終わった時には、それまでとはどこか少し違った自分になっていることに気づくはずです。
青少年読書感想文全国コンクール・感想文Q&A
この文章を読んで、読書感想文の書き方がわかる子どもは少ないと思います。
その上、この文章には高学年でしか読めない言葉や漢字がたくさん使われていますし、読みがなもつけられていませんので、きちんと読めない子どももたくさんいると思います。
明確に書き方も伝えないまま、夏休みの宿題として出すのは、とても心ない指導のように思います。
<読書感想文の書き方>
読書感想文の書き方があるわけではありません。
ここに書くことはあくまで、私の個人的な考えです。
しかし、全く何も教えないまま読書感想文を書くようにするよりもよいのではないかなと思います。
私は、「読書感想文の書き方例」としては、次のようにすればいいのではないかなと思います。
1.この本を読んだきっかけ
2.この本を読んで最初に思った感想
3.この本の主人公や登場人物が体験したこと
4.この本の主人公や登場人物と同じように体験したことやそれについて思うこと
5.自分と主人公や登場人物と似ていること、違うこと
6.この本を読んで学んだこと
当然ですが、これはあくまで4~6年生の子どもを想定した書き方の一例です。この通りにする必要はありません。
ただ、どのように書けばいいかわからない子どもにとっては、具体例があることで書きやすくなるのではないかな、と思います。
<1.この本を読んだきっかけ>
なぜ、この本を読むことにしたのかを書きます。理由は、いろいろあるでしょう。
題名がおもしろそうだったから。家族にすすめられたから。課題図書の一冊だったから。映画やドラマで見て、原作を読んでみたいと思ったから。
なんでもいいと思います。素直に、なぜ、その本を手にしたのかを書けばいいと思います。
<2.この本を読んで最初に思った感想>
読書をすることは、新しい考えや感じ方を知ることでもあります。ですから、最初に思った感想は、今までの自分と少し変化した経験をすることでもあります。
最初に思った感想を書くことも比較的簡単なことのように思います。
むずかしかったという感想しか出てこないのであれば、その本は、まだ今の自分には合っていないのかもしれません。もっと自分に合う本に変えてみるというのも一つの考えかもしれません。
<3・4.この本の主人公や登場人物が体験したことやそれについて思うこと>
よい読書感想文を書くポイント1つは、体験や経験を書き加えるということです。
読書感想文を書くことになると、多くの人は、本のあらすじをまとめて、それに簡単な感想をつけようと思うのではないでしょうか。
本のあらすじに、簡単な感想だけでも、立派な読書感想文だと思います。
でも、できればもっと読みごたえるのある読書感想文にしてほしいです。
あらすじに簡単な感想をつけたものが、なぜだめなのかというと、どの子が書いたものもだいたい似てくるからです。
2022年の高学年の課題図書に「りんごの木を植えて」(大谷美和子作・ポプラ社・2021年)という本があります。
大好きなおじいさんにがんの再発が見つかります。でも、おじいさんは積極的な治療はしないと決めました。主人公のみずほさんはそれが納得できません。
「体験を書きましょう。」と言われても、祖父ががんになった人は、あまりいないかもしれません。そんな場合でも、家族が病気になった経験はあるでしょう。病気になって自分はどう感じたかは人によって違うと思います。それを正直に書けばいいのです。
家族が病気になったことがなくても、もし家族ががんになって、治療はしないと言われたらどう思うかを書くのです。
体験はみんな違います。そうすると、同じ本を読んだ感想文もみんな違ってくるのです。
主人公や登場人物は様々なことを体験します。その中で気になったことを取り上げ、それについて書けばいいのです。
<5.自分と主人公や登場人物と似ていること、違うこと>
よい読書感想文を書くポイントの2つめは、「主人公や登場人物と自分を比べて書く」ということです。
東京書籍の4年生の教科書に載っている村中季枝さんが書かれた「走れ」という作品を例にして考えてみます。
走れ 教材分析054に進む(内部リンク)
この物語の登場人物は、のぶよさんと弟のけんじさんです。
のぶよさんの家族は、のぶよさんとお母さんと弟のけんじさんです。
お父さんがなくなってから、のぶよさんのお母さんは、駅前で弁当の仕出し屋さんをしています。
弟のけんじさんは、2年生ですが、のぶよさんと違って、とても足が速いです。
昨年の運動会は、仕事でお母さんは、学校に来るのが遅くなりました。
走る姿を見てもらえなかったけんじさんは、泣きだしました。
今年、お母さんは、運動会に来て、けんじさんの走る姿をみることになっていました。
しかし、やっぱり仕事で来ることが遅くなり、けんじさんは怒ってしまいます。
あなたが、もしけんじさんと同じような経験をしたら、どのように感じるでしょうか。
物語を読んで、気持ちが大きく揺さぶられる場面を選び、自分ならどうするか考えて書きます。
今回取りあげた「走れ」で出てきたけんじのように、約束を破られた経験をしたら、どう思うか考えてみるのです。
自分が同じような立場になったら、どう感じたり、行動したりするか考えてみるのです。
そして、けんじさんは、こんな行動をしたけれど、自分ならこうすると、登場人物と自分を比べて書きます。
みんな感じ方は違うので、読んだ人の数だけ違う行動が考えられます。
そうすると、同じ本を読んだ読書感想文でも、みんな違ってきます。
<6.この本を読んで学んだこと>
読書をすることで、今までの感じ方と変わったことがあるのではないでしょうか。新しいことを知ったかもしれません。今まで思いもしなかった、新しい気持ちを感じるようになったかもしれません。
戦争に関係する本を読めば、平和の大切さを強く願うようになるかもしれません。
けんかに関係する本を読めば、仲良くすることの大切さについて考えるようになるかもしれません。
そのように、本を読むことで学んだことを素直に書けばいいと思います。
<まとめにかえて>
読書感想文の書き方について、明確な方法があるわけではありません。
ただ、何も教えず、「自由に書いてきていいんですよ。」と伝えることは少し教員として手抜きのような気がします。少なくとも、どのようなポイントで書くようにすればいいのか伝えることは、大切なような気がします。
なお、私が子ども用に作っている「よみもの」で「読書感想文の書き方」について書いた文章があります。
読書感想文の書き方①に進む(外部リンク・よみもの)
読書感想文の書き方②に進む(外部リンク・よみもの)
読書感想文の書き方③に進む(外部リンク・よみもの)
読書感想文の例に進む(外部リンク・よみもの)
参考になれば、うれしいです。
⭐️ ⭐️
作文の指導については、次のページもお読みください。
作文のすすめ(1)400字作文に進む(内部リンク)
作文のすすめ(2)400字作文の実際に進む(内部リンク)
作文のすすめ(3)指導前に、自分が書いてみるに進む(内部リンク)
作文のすすめ(4)書きたいことがある状態にするに進む(内部リンク)
作文のすすめ(5)構想表についてに進む(内部リンク)
作文のすすめ(6)自由作文に進む(内部リンク)
作文のすすめ(7)子どもの発達段階を知るに進む(内部リンク)
作文のすすめ(8)低学年向けに進む(内部リンク)
作文のすすめ(9)中学年向けに進む(内部リンク)
作文のすすめ(10)高学年向けに進む(内部リンク)
作文のすすめ(11)卒業文集に進む(内部リンク)
作文のすすめ(12)4こま漫画に進む(内部リンク)
作文のすすめ(13)意見文に進む(内部リンク)
作文のすすめ(14)感想文に進む(内部リンク)
作文のすすめ(15)縦書きと横書きに進む(内部リンク)
作文のすすめ(16) 日記の指導に進む(内部リンク)
作文のすすめ(17)系統を考えた指導に進む(内部リンク)
作文のすすめ(18) お気に入りの表現に進む(内部リンク)
作文のすすめ(19)提案文に進む(内部リンク)
作文のすすめ(20)新聞を作ろうに進む(内部リンク)
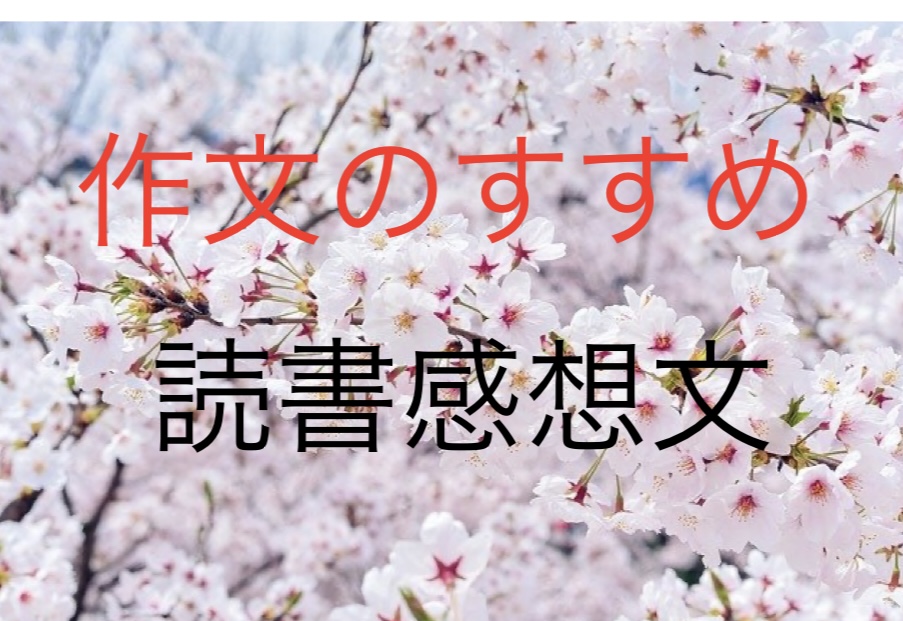
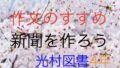
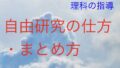
コメント