
新しい教材の「春風をたどって」の教材分析について知りたいです。
よい授業をするためには、ていねいな教材研究をすることは大切です。
しかし、国語の教材の分析をするのは時間がかかります。
そこで、大まかな教材分析例を提示することにします。
今回は、「春風をたどって」の教材分析をします。
この教材は、2024年(平成6年)の4月から採択されている教科書で新たに付け加えられた教材です。
春風をたどって:教材分析

🟠春風をたどって:教材分析
この作品は、光村図書の3年生の教科書に載っています。2024(令和6)年からの新教材です。
<作者>
如月かずさ(きさらぎ・かずさ)さん作
かめおか あきこさん絵
出典:この教科書のための書き下ろしです。
如月かずささんについて
1983年(昭和58年)生まれです。日本の児童文学作家です。
群馬県桐生市で生まれました。地元の小・中・高校を卒業しています。
東京大学教養学部(表象文化論)卒業後、東京大学大学院総合文化研究科博士課程に進学し、単位取得後退学されています。
2009年(平成21年)に「サナギの見る夢」で第49回講談社児童文学新人賞佳作、「ミステリアス・セブンスー封印の七不思議」(岩崎書店)で第7回ジュニア冒険小説大賞を受賞されています。
2011年(平成23年)に「カエルの歌姫」(講談社)で第45回日本児童文学協会新人賞を受賞されています。
その他の作品に「なのだのノダちゃん」シリーズ(小峰書店)、「ミッチの道ばたコレクション」シリーズ(偕成社)、「給食アンサンブル」シリーズ(光村図書出版)などがあります。
<題名>
題名は「春風をたどって」です。
この題から、誰かが春風の後をたどって旅をしているような感じを受けます。誰が、どのような目的で春風についているのか興味がわく題名です。
<設定>
いつ(時):お昼ごはんの前。(後からわかる)
どこ(場所):森の中の高い木のえだ。
だれ(登場人物):りすのルウ
<人物>
りすのルウ……主人公。旅に出たいと思っている。
森で一番のもの知りりす……ルウに海や雪山やさばくのことを教えてくれる。
ノノン……ルウのなかまのりす。とてものんびりおっとりしたりす。
<あらすじ>
・「旅に出たい。」りすのルウは、さいきん、そんなことばかり言っている。
・心うきうきさせる春風がルウのしっぽをくすぐり、ルウはたから物のことを思い出す。
・ルウのたから物は、風でとばされてきたたくさんのしゃしん。
・しゃしんには、青い海、白一色の山々、黄金にかがやくさばくなどのけしきがうつっている。
・見なれたけしきをながめ、ルウはためいきをつき、「いつか、しゃしんのけしきを見に行く」と思うが、おなかが鳴ったので、木のみをさがしにいくことにした。
・「さいしょに行くのは、海がいいな」と思いながらルウが森を進んでいくと、顔見知りノノンを見かける。
・ノノンは、とてものんびりおっとりしたりすだ。
・ノノンは、ねむっているように目をとじているが、よく見るとはながくんくんと動いている。
・「何をしているの」と聞くと、「びっくりした。あのね、すてきなにおいがする。」とのこと。
・ルウにはにおいがしないが、ノノンは、ガサガサと近くのしげみに入っていく。
・前が見えなほどの深いしげみを進むと、ルウも知らないにおいに気づく。
・さわやかで、ほんのりあまり、とてもすてきなにおいだ。
・「ノノンは、こんなかすかなにおいに、気づいてたんだ。」とルウはびっくりする。
・しげみは、どこまでもつづき、ルウはつかれてくるが、ノノンは足を止めるけはいもない。
・しげみがやっととぎれたかと思うと、あざやかな青が目にとびこんでくる。
・しげみのむこうには、見わたすかぎりの花ばたけ。ルウが行きたいとねがっていた海にそっくりな青。けしきのうつくしさに、ルウの口から、ほう、とためいきがこぼれる。
・ノノンは、うっとりと花ばたけを見とれている。
・ルウは、ぼく一人だったら、この花ばたけを見つけることはできなかったと思う。
・しばらくして、ノノンがのんびりと言う。「そろそろお昼ごはんをさがしに行こうかな。」
・ルウは、「ぼくは、もう少しここにいることにする」と答える。
・ノノンを見おくり、ルウは、花ばたけをながめる。
・さわやかな春風が花たちとルウの毛を、さわさわとなでていく。
・花ばたけの空気をすいこみ、本物の海もこんないいにおいがするのかなと、ルウはそうぞうする。
・その夜、ルウは、すあなでたから物のしゃしんをながめていた。
・きれいだなあ、いつか行ってみたいなあ、とうっとりしつつ、「だけど、あの海色の花ばたけけも、とってもすてきだったなあ。」とつぶやいた。
・「そうだ、ぼくの知らないすてきなばしょが、ほかにもまた、近くにあるかもしれない。あした、ノノンをさそって、いっしょにさがしてみることにしよう。ノノンといっしょなら、あの花ばたけみたいなけしきを、見つけられそうな気がするから。」
・そんなふうに考えてわくわくしながら、ルウがねどこにねそべると、花ばたけからついてきたさわやかなかおりが、ふわりとルウのはなをくすぐった。
<場面>
この物語は、場面と場面の間に1行空きで、4つの場面に分けて書かれていますので、場面を4つに分け、1場面を30~40字程度にまとめてみます。
① りすのルウは、たからもののしゃしんにうつるけしきを見てから旅したいと思っていた。
② 顔見知りのりすのノノンに会うと、いいにおいがすると、においの方に進んでいった。
③ やがてあざやかな青い色の花ばたけを見つけ、ルウは、ノノンはすごいなと思った。
④ 夜、すあなで、ルウは、ノノンといっしょにすてきなばしょをさがしてみたいと思った。
1234567890123456789012345678901234567890
<人物の会話>
この物語には重要な会話がいくつかあります。
大切な会話の一つは、主人公のルウの独り言です。もう一つは、ルウともう一人の登場人物であるノノンとの会話です。
まず、大切なルウの独り言をいくつか載せます。
・「旅に出たいなあ。」
・「それ(※しゃしんにうつるけしき)にくらべて、この森のけしきってさ、ぜんぜんわくわくしないよね。」
・「それでもぼくは、いつかぜったい、しゃしんのけしきを見に行くんだ。」
これらは、ルウが最初に思っていたことです。これが最後には、次のように変わりました。
・「そうだ。ぼくの知らないすてきなばしょが、ほかにもまだ、近くにあるかもしれない。あしたノノンをさそって、いっしょにさがしてみることにしよう。ノノンといっしょなら、またあの花ばたけみたいなけしきを、見つけられそうな気がするから。」
次に、ルウとノノンの会話を書きます。
・「ノノン、何をしてるの。
「わあ、びっくりした。あのね、なんだかすてきなにおいがするんだよ。」
「めずらしいにおいは、とくにしないみたいだけど。」
「においが弱くて分かりづらいんだよ。でも、本当にすてきなにおいなんだ。たぶん、こっちの方からしてくるんじゃないかな。」
<人物の行動>
主人公のルウのはじめの行動は、あまり関心できるものではありません。たから物のしゃしんを見て、いつも「旅に出たいなあ。」と言ったり、見なれたけしきをながめて、ためいきをついたりしていたからです。
それが一変したのは、のんびりでおっとりしたノノンが「なんだかすてきなにおいがする」と言って、しげみの中を進むについていってからです。
しげみのむこうには、見わたすかぎりの花ばたけがありました。
自分一人では何もできなかったのに、ノノンについて行くことで、すてきな花ばたけを見つけることができました。
<主題>
この物語の主題は、何でしょうか?
「旅へのあこがれ」ということかもしれません。
しかし、ルウ一人だけでは、ただあこがれているだけで何も変わりませんでした。
知り合いのノノンについて行くことで、花ばたけを見つけたルウは、次のように思います。「ぼくの知らないすてきなばしょが、ほかにもまだ、近くにあるかもしれない。あした、ノノンをさそって、いっしょにさがしてみることんしよう。」
一人では解決しなかったことが、友だちといっしょに行動することで解決することもあるということかもしれません。
それが、この物語の主題なのかもしれません。
あるいは、題名にあるように「春風をたどって」においを追いかけると、すてきなことが起こることがあるということかもしれません。
3年生は、主題を考える必要はありませんが、いろいろと考えてみるのも面白いかもしれませんね。
<表現の工夫>
この物語文には、さまざまな表現の工夫があります。
一つは、自然の様子が、擬人法を使って、とても素敵に表現されています。
例えば、次のような表現です。
・心をうきうきさせるような春風が、高い木のえだにすわったルウのしっぱをくすぐっていきます。
・しげみがやっととぎれたかと思うと、あざやかな青い色が、ルウの目にとびこんできました。
・やわらかな春風が、花たちとルウの毛を、さわさわとなでていきます。
擬人法を使った表現は、人物の様子の表現にも使われています。
・ルウのしっぽは、いつのまにか、ゆらゆらとおどるようにゆれています。
<まとめにかえて>
この教材分析は、このブログに載せている「物語文の教材研究の仕方」に挙げた10個の視点のうち、最後の指導計画を除いた9つの視点に基づいて行ったものです。
教員のみなさん1人1人が自分で行う教材研究の参考になれば幸いです。
⭐️ ⭐️
物語文の教材研究については、次のページをお読みください。
物語文の教材研究の仕方(1)基本的な考えに進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(2)視点に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(3)設定・人物に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(4)あらすじ・場面に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(5)会話・行動に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(6)主題に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(7)表現の工夫に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(8)指導法に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(9)指導方法に進む(内部リンク)
物語文の教材研究の仕方(10)目標と教材の関係に進む(内部リンク)
他の教材の教材分析については、次のページをお読みください。
まいごのかぎ 教材分析052に進む(内部リンク)
きつつきの商売 教材分析033に進む(内部リンク)
モチモチの木 教材分析019に進む(内部リンク)
すいせんのラッパ 教材分析036に進む(内部リンク)
おにたのぼうし 教材分析018に進む(内部リンク)
白いぼうし 教材分析031に進む(内部リンク)
初雪のふる日 教材分析001に進む(内部リンク)
ふきのとう 教材分析034に進む(内部リンク)
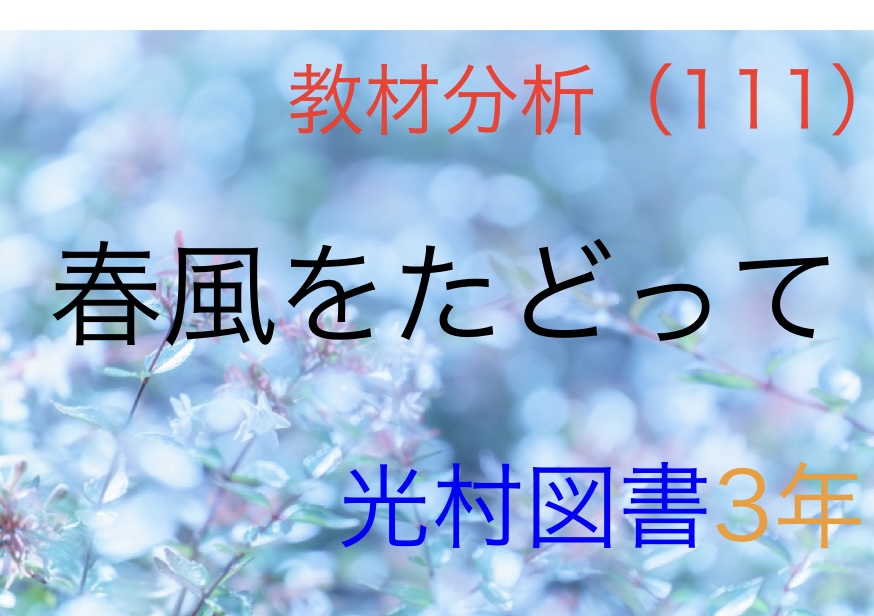
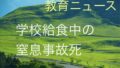
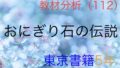
コメント